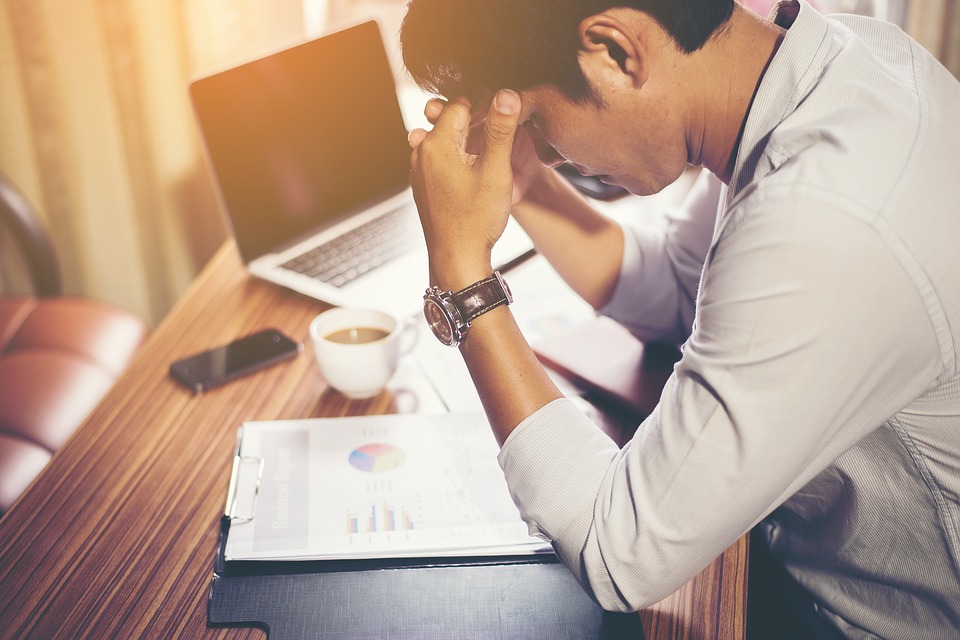睡眠薬を使いたくない人の心理について。不眠が続く場合のひとつの効果的な治療法は睡眠薬を飲むこと。しかしながら、睡眠薬で治療せず、眠れない状態を我慢している人も多くいます。
不眠が長く続くと体調を壊してしまい、日常生活にさまざまな影響がでてくるでしょう。原因が明らかに病気ではない不眠が続いているなら、医師による睡眠薬の処方で早く解消することがすすめられています。ここでは、睡眠薬を使いたくないと思う人の心理をご説明します。
不眠なのに睡眠薬を使いたくない人の心理

睡眠薬は怖いという心理
一般的に、睡眠薬は「怖い」という心理になる人は少なくありません。その理由のひとつに、睡眠薬を大量に飲んだ「睡眠薬自殺」が広く知られており、睡眠薬への悪いイメージが大きくなっていることがあります。
実際、以前使用されていた睡眠薬は「バルビツール酸系」と呼ばれた麻酔薬の一種です。脳全体の働きを低下させて眠らせるため、薬を多量に飲んだ場合は命にかかわることがありました。
しかしながら、現在使用されている睡眠薬の多くは「ベンゾジアゼピン系」の薬で、脳神経の興奮を抑える働きがあります。感情の変化やストレスなどによる脳神経の興奮を抑制して、眠りを誘ってくれるというもの。
自然に眠りを起こしてくれるため、誤って少し多めに飲んだとしても命に危険はないといわれています。
薬がだんだん効かなくなるのではないかという心理

睡眠薬に対して抱く不安で多いのが「薬がだんだん効かなくなるのではないか」「薬の量が増えていくのではないか」という心理です。
一般に、「量を増やさなければ薬が効かなくなる」というとき、「耐性ができる」という意味で使われます。病気の治療で使用される薬の中には、耐性ができる傾向のあるものもあります。
しかしながら、睡眠薬のベンゾジアゼピン系の薬は医師の指示に従って服用しているなら、耐性ができるということはありません。
薬なしでは眠れなくなるのではないかという心理
「一度飲み始めると、薬なしでは眠れなくなるのではないか」という心理になる人も多くいます。結論から言うと、睡眠薬は一生飲み続けなければならないものではありません。
睡眠薬の治療をしていく中で、ストレスと上手に付き合う方法を身につけるようになりますし、生活リズムや環境などを整えるよう心がけることでしょう。少しづつ不眠が改善されて、薬の量も減らしていくことができます。
幻覚があらわれるのではないかという心理
薬の治療を続けていても、なかなか不眠が改善されず、薬の服用が長期間になることもあります。この場合、自分の判断で薬の量を減らしたくなったり、焦って気に病んだりしてしまうことがあります。
処方を守っているなら、長い間服用していても、体調がおかしくなったり、幻覚が現れたりすることはありません。
薬がないと不安でしかたがないという心理

睡眠薬を飲んでいる場合、中毒症があらわれることはありませんが、「薬がないと不安でしかたがない」という心理になる人もいます。この場合、医師に相談するなら、徐々に減らしていって、不安の強いときだけごく少量を使用することがあるでしょう。
またごくまれですが、副作用として興奮状態になることがあります。薬の服用を止めるとおさまりますし、基本的に、ベンゾジアゼピン系の睡眠薬は少量であれば一生飲み続けても比較的安全であるといわれています。
なるべく薬局で買えるものがいいという心理
不眠の治療で使用されるベンゾジアゼピン系の薬などは医師の処方がないと買うことができない薬。「病院に行くのは面倒だ」「なるべく薬局ですませたい」という心理から、薬局で買えたらいいのにと思ってしまう人もいます。
薬局で購入する場合、精神をリラックスさせて寝つきを良くする薬があります。鎮静薬という種類で、興奮やイライラ感、緊張感を鎮めてくれます。
しかしながら、風邪をひいて他の薬を服用していたり、持病があったりするときは飲むことができません。その薬に鎮静作用を持っているものもあり、強い催眠作用になることがあるからです。
また、鎮静薬はあくまでも一時的な使用にとどめましょう。数回使用しても不眠が続くようであれば、必ず医師に相談してください。
アルコールを飲めなくなるのではないかという心理

間違った睡眠薬の使用は問題を起こしてしまいます。特に、睡眠薬を服用しているときにアルコールを飲むことは絶対避けなければなりません。
そもそも、アルコールは脳を麻痺させるため寝つきは良くなるかもしれませんが、浅い眠りばかりで良い睡眠ではないでしょう。アルコールと睡眠薬との併用は、薬の作用を強くしすぎたり、作用時間を長くしすぎたりする危険があります。
それでも、アルコールを飲みたいという人は晩酌など、睡眠薬を飲むまでに酔いをさましておきましょう。睡眠薬を飲む直前の寝酒や睡眠薬との併用はしないでください。
まとめ
睡眠薬は同じ種類のものでも、それぞれ特徴が異なっています。症状だけでなく、年齢や体の状態、他の薬の服用などによって薬が選択されます。気になることはいつでも医師に相談して判断してもらいましょう。